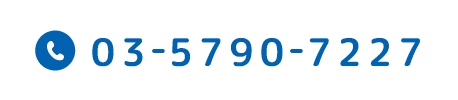一般診療
"症状"として...
"病気"として...
感染症(バイ菌やウイルスの感染による病気)
アレルギー
その他
新生児内科
この時期は、お母さんのおなかの中から、出生後の外の環境への変化に慣れていくためのとても大切な期間です。
生まれて間もない新生児は、とても弱々しく、哺乳をしたら寝るの繰り返しのようですが、日に日にいろいろな感情や動きを示してくれるようになり、保護者の方もちょっとしたことが気になってくると思います。
- いきんだり、うなったりすることが多い。
- おう吐(いつ乳)が多い。
- しゃっくりが多い。
- いつも鼻がグズグズして苦しそう。
- 呼吸がハカハカすることがある。
- うんちの回数が多い、2~3日に1回しかうんちがでない。
- 皮膚が黄色いのが気になる。
- 顔や腕のアザが気になる。
- 目やにがでる。
- 耳が臭う。
- 臍(へそ)が出ている。
また、母乳やミルクの量は足りているか、目の動きや手足の動きが気になる、などの疑問を生じることもあるでしょう。
頭の形が気になると相談される方も増えています。生後数ヵ月は特に頭の骨(頭蓋骨)が柔らかいので、向き癖、寝癖があると頭が変形してしまうことがあります。最近は、頭の形は単に見た目だけの問題だけではなく、顔の歪みからくる問題や発達にも影響する可能性があるとの報告もみられるため、なるべく早い時期から向き癖の矯正をしてあげる方がよいでしょう。
また、新生児の時から全身に1日2回以上保湿剤を塗ってあげると、皮膚の“バリア機能”が高まり、アトピー性皮膚炎の発症を減少させることが最近わかってきました。
さらに、母乳栄養児に不足しがちな、ビタミンK、鉄、ビタミンDをどのように補ってあげたらよいか? なども赤ちゃんにとってとても大切なことです。
これらのことを疑問に思っている保護者の方は、クリニックの育児・栄養相談の時間(15:00~16:30)でご相談さい。また、「赤ちゃんのために知っておきたいこと ペリネイタルビジット(PHPエディターズ・グループ)」でも、上記の疑問に丁寧にお答えしていますので参考にしていただければと思います。
小児科
感染症
感染症の原因のほとんどはウイルスによるものです。特効薬のあるウイルスはインフルエンザウイルス、水痘(みずぼうそう)ウイルス、ヘルペスウイルスだけで、その他のウイルス感染症に対しては対症療法といって、症状に応じた処置をしたり、薬を使って症状を和らげる治療を行います。ウイルス感染症の代表は風邪(上気道炎)です。
細菌が原因となる感染症には抗菌薬(抗生物質)が有効ですが、感染症のごく一部なので、熱があるからといってすぐに抗菌薬を使用することはありません。抗菌薬が有効な細菌感染症の代表は溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、百日咳です。
感染症の症状として、熱、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、腹痛、下痢、おう吐、耳の痛み、排尿時の痛み、などを認めます。
感染症の代表的な病気として、春~夏にかけては、溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱(プール熱)、アデノウイルス咽頭炎、そして皮膚の感染症としてとびひ(伝染性膿痂疹)、水いぼ(伝染性軟属腫)などが流行します。秋~冬~春には、風邪(上気道炎)、インフルエンザ、RSウイルス感染症、ヒトメタニューモウイルス感染症、ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス)などの流行がみられます。
また、突発性発疹症、水痘(みずぼうそう)、おたふくかぜなどは、季節に関係なく一年中認められます。
中耳炎は風邪が長引いた後によくみられます。鼻水がたまっていると体の中にいる細菌(肺炎球菌など)が鼻の中で繁殖し、耳管を通じて耳の内耳というところに侵入して膿がたまってしまう状態です。RSウイルス感染症の経過中に見られることが多く、抗菌薬(抗生物質)による治療が必要になることがあります。
便秘症
便秘とは、便が長い時間でないか、出にくいことをいいますが、週に3回より少なかったり、5日以上でない日が続けば便秘と考えます。ただし、毎日出ていても、硬い便で出す時に痛がって泣いたり、肛門が切れて血が出るような場合も便秘となります。
赤ちゃんに便秘がみられるときは、栄養が足りているか、生まれつきの病気が隠れていないかに注意することが大切です。離乳食の開始や回数が増えてくると便秘傾向になることがよくあります。また、トイレトレーニングをきっかけに便秘になってしまうこともあります。
治療方法は月齢や年齢、症状により異なりますが、食事療法から開始し、おなかにやさしい非刺激性下剤と腸を動かして便を出す刺激性下剤を併用して治療を行います。
夜尿症
原因は、尿の量が多すぎたり、膀胱に尿を十分にためられないことに関係しています。
夜尿症はアレルギー疾患に次いで2番目に多い子どもの慢性的な病気といわれています。
一般的に夜尿症は成長とともに自然に治りますが、小学校やクラブでのお泊りなどへの参加前に治したいと相談に来られるお子さんが多いようです。
治療は、夜の水分摂取を控えること、夕食から寝るまでの時間を2時間以上あけることなどの生活改善から始め、その後、薬を使った治療を行います。
治療開始後の半年までに80%の子どもの症状が改善した、治療後2年で75%の子どもが治った、早めに治療を開始する方が治癒率が高い、などの報告があります。
健診・栄養相談
乳幼児健診
乳幼児健診(乳幼児健康診査)は、栄養状態や発育の確認などを定期的に行うことで、子どもの健康保持及び増進を図ることを目的としています。成長で気になっていることや子育ての不安などがあるときは、予め母子健康手帳に記録して質問するようにしましょう。
3~4ヵ月健診、1歳6ヵ月の歯科健診、3歳児健診は区の保健相談所での集団健診となります。
3~4か月乳幼児健診:指定の保健相談所
皮膚の状態、追視や音への反応、首の座り、股関節の開きなどをチェックします。
6~7か月乳幼児健診:当クリニック
おもちゃなどをつかめるか、お座り、寝返りなどをチェック、離乳食の確認などをします。
9~10か月乳幼児健診:当クリニック
はいはい、つかまり立ちなどをチェック、離乳食の回数などを確認します。
1歳6か月児健診:当クリニック、または渋谷区在住以外の方は地域医療機関(当クリニックでワクチン接種を行われている方は無料です)
1人歩き、意味のある言葉をいくつ話せるかなどをチェックします。
1歳6か月歯科健診:指定の保健相談所
歯の生え方や本数、虫歯のチェックをします。
3歳児健診:指定の保健相談所
二語文を話せるか、コミュニケーション能力や自我の確立の確認などを行います。
入園・入学時健診
院長が園医・校医を担当している施設での集団健診を受診できなかった方は無料で受けられます。それ以外の方は自費診療(3,000円)となります。 私立幼稚園、私立小学校・中学校の入学健診は自費診療(3,000円)となり、診断書は1園(校)につき3,000円加算されます。
栄養相談
月に2~3日、管理栄養士が14:30~16:30の時間帯に来院します。 来院日は「栄養士来院日」でご確認ください。 予約等は必要ありませんので、直接いらしてください。 母乳やミルクの量、離乳食の進め方など、ご相談ください。
内科
感染症
家庭で子育てをしていると、子どもの感染をもらってしまうことがしばしばあります。
感染症は子どもの方が症状が重くなるものがほとんどですが、中には大人が罹った方が重症になる感染症もあります。
大人の方の診察も行っていますので、ご相談ください。
アレルギー疾患
気管支喘息、アレルギー性鼻炎(花粉症)などご相談ください。
金曜日午後のアレルギー外来もご利用ください。
その他
他院で処方の内服薬、外用薬等、処方することも可能です。
お薬手帳があればご持参ください。